【永久保存版】子どもの口臭が気になるときに知っておきたい原因と対策

はじめに:実は多い?子どもの口臭に悩む親御さん

「朝起きたとき、子どもの口が臭う気がする」「歯みがきしているのにニオイが消えない」──そんな違和感を覚えた経験はありませんか?
実は、子どもの口臭に悩む親御さんは決して少なくありません。にもかかわらず、「子どもに口臭なんてあるの?」と思って、誰にも相談できずにモヤモヤしてしまうことも多いのです。
子どもにも、一時的なものから病的なものまで、さまざまなタイプの口臭が現れることがあります。原因は、虫歯や歯周トラブルだけでなく、口呼吸・生活習慣・体調不良など多岐にわたります。
この記事では、子どもの口臭の原因から、年齢別の傾向、家庭でできる対策、そして歯科での対応まで、丁寧に解説します。
子どもにも口臭はある?正常な口臭と異常な口臭の違い
「子どもなのに、口が臭うのはおかしいのでは?」と思うかもしれませんが、実は子どもにも口臭はあります。
しかも、大人と同じように「正常な口臭」と「異常な口臭」の2種類が存在します。
正常な口臭とは
口臭は、誰にでも少なからずあるものです。たとえば以下のような場面では、子どもでも一時的に口がにおうことがあります。
- 朝起きた直後(唾液の分泌が少なくなるため)
- 空腹時
- 運動後や発熱後の脱水状態
- 緊張したとき(唾液の分泌が一時的に減る)
これらは生理的口臭と呼ばれ、健康な体の反応です。水分補給やうがい・歯みがきで改善することが多く、心配はいりません。
異常な口臭とは
一方で、以下のような場合は注意が必要です。
- 歯みがきしてもニオイが残る
- 毎日におう・ニオイが強くなる
- 甘酸っぱい、腐敗臭のようなニオイがする
- 口臭に加えて、歯や歯ぐきのトラブルが見られる
このようなケースでは、病的な口臭の可能性があります。原因として、虫歯・歯肉炎・口呼吸・扁桃炎・副鼻腔炎など、何らかの体の異常が関係していることもあります。
つまり、子どもの口臭は「よくあること」でもありますが、「放置してはいけないサイン」でもあるのです。違和感を覚えたら、まずは観察し、必要に応じて歯科や耳鼻科などに相談することが大切です。
口臭の原因① 口腔内のトラブル
子どもの口臭で最も多い原因は、口の中のトラブルにあります。とくに、歯みがき不足や虫歯は代表的です。
歯みがきが不十分だと、どうなる?
子どもはまだ手先が不器用なこともあり、しっかり歯を磨けていないことが多くあります。さらに、仕上げみがきの習慣がない場合、磨き残しによりプラーク(歯垢)や食べカスがたまりやすく、そこに細菌が繁殖して口臭が発生します。
特に注意すべきポイントは以下の通りです:
- 奥歯の噛み合わせ部分(臼歯の溝)
- 歯と歯の間(フロスが必要な部位)
- 歯と歯ぐきの境目
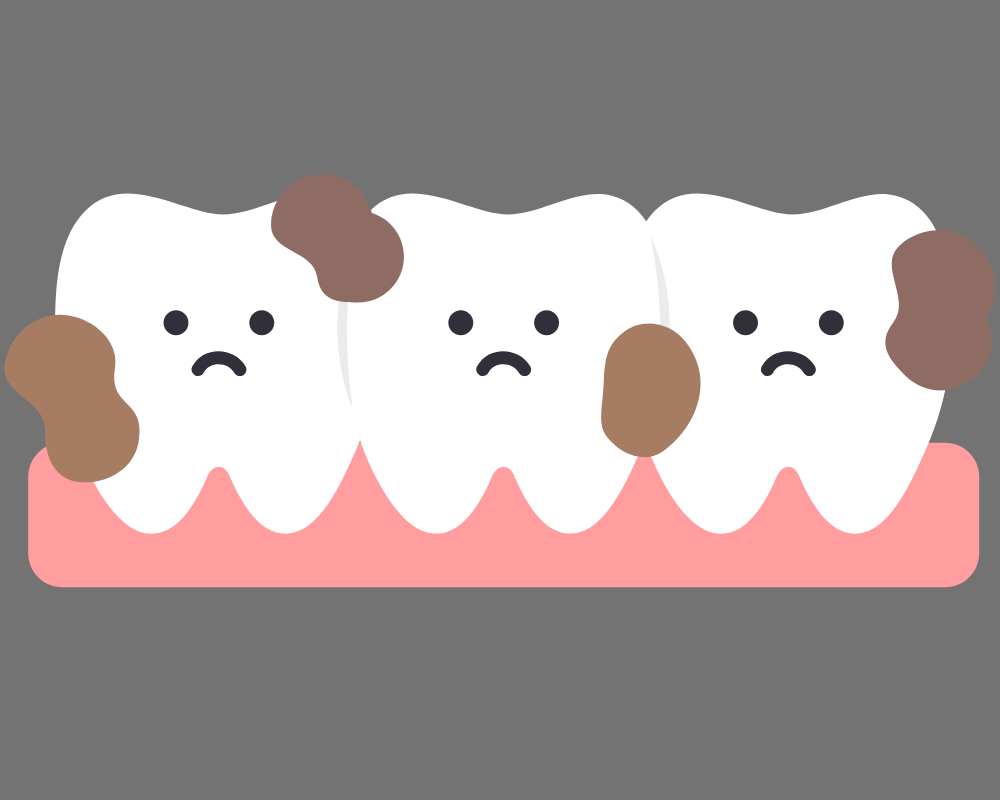
虫歯や歯肉炎もにおいの原因に
進行した虫歯では、歯の内部で細菌が増殖し、強い腐敗臭のようなにおいを放つことがあります。また、歯ぐきに炎症がある場合も、歯周病原菌の働きによって硫黄のような独特なニオイが出ることがあります。
以下のような症状がある場合は、歯科医院でのチェックをおすすめします:
- 甘いものを食べたときに歯がしみる・痛む
- 歯ぐきが赤い、または腫れている
- 口の中を気にしている様子がある
舌苔(ぜったい)による口臭
舌の表面に付着する白色や黄白色の細菌や食べかすの塊を「舌苔」と呼びます。特に舌の奥の方にたまりやすく、ここで細菌が繁殖すると、口臭の原因となる揮発性硫黄化合物が発生します。
子どもでも舌苔はできやすく、特に以下のような場合に増えやすい傾向があります:
- 起床時に口の中が乾燥している
- 体調不良や風邪をひいている
舌苔は歯ブラシや専用の舌クリーナーでやさしく取り除くことが効果的です。ただし、強くこすりすぎると舌を傷つけるため注意が必要です。
日々のケア+定期チェックがカギ
子どもの口臭を防ぐには、まず家庭での丁寧なブラッシングが基本です。小学生の間はできるだけ保護者が仕上げみがきをし、月1回のチェックでもよいので、歯科医院での定期的なメンテナンスを受けると安心です。
口臭の原因② 鼻・喉の病気
口の中だけでなく、鼻や喉の不調が口臭の原因になることもあります。特に、風邪をひいたときやアレルギーがある子どもに見られやすいです。
副鼻腔炎(蓄膿症)による口臭
副鼻腔炎とは、鼻の周囲にある空洞(副鼻腔)に膿がたまる病気で、「蓄膿症」とも呼ばれます。膿が鼻の奥にたまり、そのにおいが喉を通って口から出てくるため、口臭として感じられます。
以下のような症状がある場合、副鼻腔炎の可能性があります:
- 鼻づまりや黄色〜緑色の鼻水が続く
- 鼻の奥や目の周りが痛い・重たい
- 口で息をしている(いびきが大きい)
この場合は、歯科よりもまず耳鼻科の受診が必要です。
扁桃腺の腫れ・膿栓(のうせん)
扁桃腺の表面にある小さな穴に、食べかすや細菌の死骸がたまってできる白いかたまりを「膿栓(のうせん)」といいます。これができると、強いにおいを伴うことがあり、子どもでも気づくほどの口臭になることがあります。
膿栓はとくに以下のようなときにできやすいです:
- 風邪やのどの炎症を繰り返している
- いびきが多く、口呼吸になりがち
- 扁桃腺が生まれつき大きい
無理に取ろうとせず、耳鼻咽喉科での診察を受けることが大切です。
口呼吸と口臭の関係
鼻づまりや鼻炎などが原因で口呼吸になっていると、口の中が乾燥しやすくなります。唾液には口内の細菌を洗い流す役割がありますが、口呼吸で乾燥するとこの作用が弱まり、細菌が増殖しやすくなり口臭の原因となります。
また、口呼吸は鼻・喉の病気と深く関係しており、鼻づまりを改善しない限り口呼吸が続くため、口臭も改善しづらくなります。
鼻や喉の病気が疑われる場合は、歯科と並行して耳鼻科の受診も検討しましょう。
口臭の原因③ 胃腸や全身の不調
子どもの口臭は、胃腸の不調や全身状態の変化によっても引き起こされることがあります。頻度は高くありませんが、注意が必要なケースです。
胃腸の働きの乱れ
食べ過ぎや消化不良、便秘など、消化器系のトラブルが口臭の原因になることがあります。特に以下のような場合、胃腸由来の口臭が疑われます:
- 朝起きたときの口臭が強い
- 食べたものがなかなか消化されていない
- おなかの張りや便秘が続いている
食生活の見直しや、必要に応じて小児科の相談が効果的です。
空腹時の生理的な口臭
意外に思われるかもしれませんが、空腹の時間が長いときにも口臭が出ることがあります。これは唾液の分泌が減り、口の中が乾燥しやすくなるためです。
例えば:
- 朝食を抜いたまま登校したとき
- 寝起き直後で水分をとっていないとき
このような場合は、水分補給や軽い食事で改善することが多いです。
糖尿病・肝疾患などの病気による口臭(まれなケース)
まれですが、糖尿病や肝臓の疾患があると、特有の甘酸っぱい・アンモニア臭のような口臭が出ることがあります。ただし、こうした病気は他にも全身症状(体重減少、だるさ、皮膚の異常など)を伴うため、口臭だけで判断することはできません。
気になる症状が他にもある場合は、早めに小児科での精密検査を受けることが大切です。
まれに、逆流性食道炎や胃腸の不調によって口臭が出ることもあります。これらは内科的な原因ですが、小学生以上の子どもであれば、ストレスや食生活の乱れにより発症することがあります。
年齢別に見る、子どもの口臭の傾向と原因
乳幼児(0〜3歳)

・口腔ケアが未発達
・哺乳瓶・指しゃぶりによる口呼吸
・扁桃腺の肥大など
基本的には生理的口臭が多く、病的なものはまれです。
幼児〜小学生(4〜10歳)
- 乳歯の虫歯
- 舌苔の蓄積
- 歯磨きの不徹底
この時期は自分で歯磨きをするようになり始める時期なので、保護者の仕上げ磨きが非常に重要です。
思春期(11歳〜)
- 永久歯の虫歯や歯肉炎
- 思春期特有のホルモンバランスによる口腔内の変化
- ストレスによる胃腸障害
この時期は大人と同様の口臭の原因を持ちやすくなります。
子どもの口臭のチェックポイントと対処法
お子さんの口臭が気になるとき、親御さんが確認しておきたいポイントと、家庭でできる対処法を紹介します。
【1】まずは“いつ・どんなとき”に臭うか確認
口臭の強さやタイミングにはヒントが隠れています。以下のような点をチェックしてみましょう:
- 朝起きた直後だけ臭うのか、それとも日中も続くのか
- 特定の食べ物の後に臭うのか
- 病気や体調不良が関係していないか
朝だけ臭う場合は生理的口臭の可能性が高く、心配のいらないケースもありますが、日中も強い臭いが続く場合は何らかの原因があるかもしれません。
【2】歯磨きや口腔ケアの状況を見直す
子どもの口臭で最も多い原因は「磨き残し」です。次のような点を確認してみましょう:
- 歯ブラシの使い方(正しい持ち方・動かし方)
- 歯と歯の間や奥歯がしっかり磨けているか
- 舌苔(舌の白っぽい汚れ)がついていないか
仕上げ磨きを継続すること、フロスの使用や舌みがきを取り入れることも有効です。
【3】食生活・生活習慣も見直そう
偏った食事や水分不足、睡眠不足も、口臭を引き起こす要因になります。以下のようなポイントを意識してみてください:
- よく噛んで食べる
- 水やお茶をこまめに飲む
- 寝る前の食事は控える
- 十分な睡眠をとる
生活習慣が整うと、自然と口臭が軽減するケースもあります。
【4】それでも気になる場合は歯科医院・小児科へ
家庭でのケアをしても改善しない、または口臭が急に強くなった場合には、歯科医院や小児科の受診をおすすめします。
- むし歯や歯周病の有無をチェック
- 扁桃腺や鼻の疾患、胃腸のトラブルがないか検査
- 必要に応じて耳鼻咽喉科や内科との連携
早期発見・早期対応で安心につながります。
家庭でできる!子どもの口臭対策5つ

① フロスを取り入れた丁寧な歯磨き
歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは取れません。仕上げ磨きの際にフロスを取り入れることで、プラーク除去率が大幅にアップします。
② 口呼吸の改善
鼻づまりが原因であれば耳鼻科への相談を、癖であれば口唇閉鎖のトレーニング(口輪筋トレーニング)なども効果的です。
③ 舌のケア
舌苔が目立つ場合は、柔らかい舌ブラシやガーゼを使って優しくふき取ってあげましょう。ゴシゴシこすらず、週に数回程度で十分です。
④ 食生活の見直し
甘いお菓子やジュースの頻度を見直し、唾液の分泌を促す食材(梅干しなど)や、歯の再石灰化を促進するリカルデントガムなどを取り入れるのも有効です。

⑤ 定期的な歯科受診
歯科医院での定期検診は、虫歯の予防と早期発見だけでなく、口臭の原因チェックにも有効です。プロによるクリーニングで舌苔やプラークの除去もできます。
歯科医院でできる子どもの口臭ケア
歯科医院では何をするの?
・虫歯・歯肉炎のチェックと治療
・舌苔・プラーク・歯石の除去
・歯磨き指導(ブラッシング指導)
歯科医院に慣れていないお子さんは、まず慣れるところから始めます。
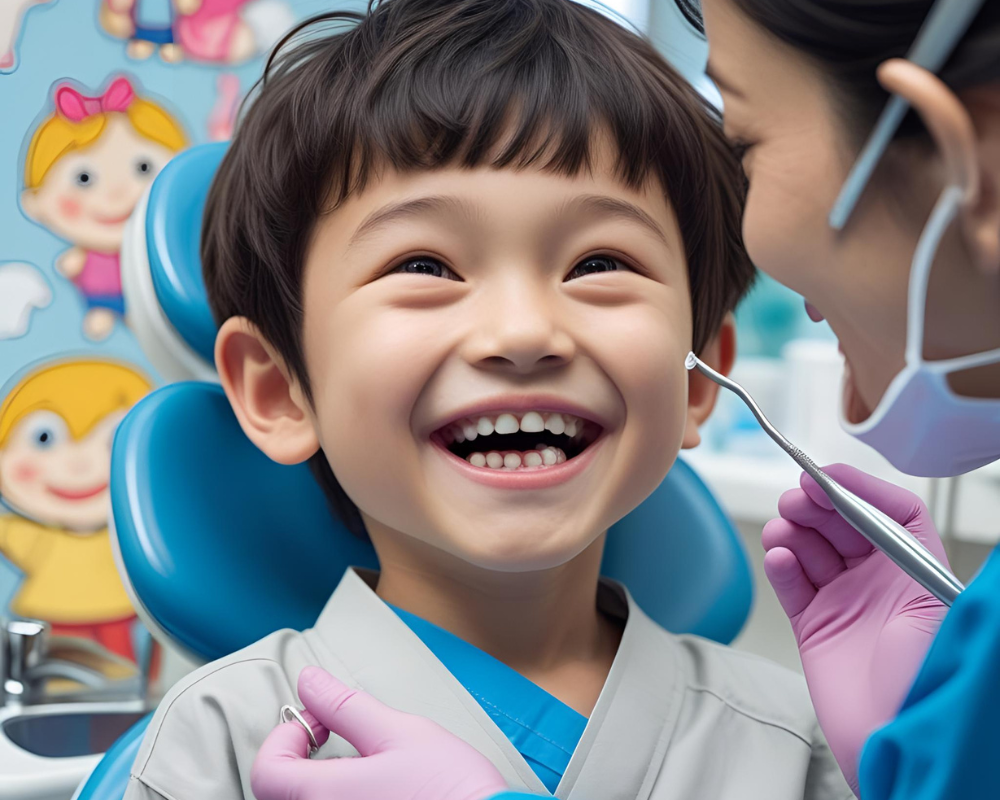
耳鼻科や小児科と連携する場合も
副鼻腔炎や扁桃腺炎などが原因の場合、歯科だけでなく耳鼻科や小児科との連携が必要になることもあります。口臭が長引く場合は複数科への相談も検討しましょう。
子どもの口臭、もう悩まなくて大丈夫です
「子どもの口臭が気になるけど、どうしたらいいかわからない…」そんな不安を抱える親御さんは多いはずです。放っておくと、お子さんの自信や日常生活にも影響が出ることがあります。
しかし、ご安心ください。子どもの口臭は、原因をしっかり知り、正しいケアを続ければ、必ず改善できます。虫歯や歯肉炎の治療、舌の汚れの除去、正しい歯磨き習慣の定着で、お子さんの口臭はコントロール可能です。
「子どもだから自然に治る」と自己判断せず、まずは専門家に相談することが何よりも大切です。
※画像引用
・GC公式HP
・リカルデント公式HP
